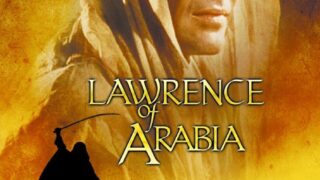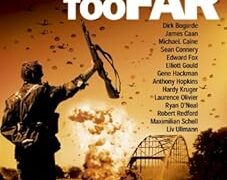恐竜の骨と豹が巻き起こす大騒動!スクリューボール・コメディの最高峰

生真面目な古生物学者と、彼を翻弄する天真爛漫な令嬢、そしてペットの豹(ベビー)が繰り広げる予測不能のノンストップ・コメディ。ハワード・ホークス監督が放つ、映画史上最もチャーミングで騒々しい傑作。
赤ちゃん教育
Bringing Up Baby
(アメリカ 1938)
[製作] ハワード・ホークス
[監督] ハワード・ホークス
[原作] ヘイジャー・ワイルド
[脚本] ダドリー・ニコルズ/ヘイジャー・ワイルド
[撮影] ラッセル・メティ
[音楽] ロイ・ウェッブ
[ジャンル] 恋愛/コメディ
キャスト

キャサリン・ヘプバーン
(スーザン)

ケーリー・グラント
(デヴィッド)
チャールズ・ラグルズ (アップルゲイト)
ウォルター・キャトレット (スローカム)
バリー・フィッツジェラルド (ゴガーティ)
メイ・ロブソン (エリザベス伯母)
フリッツ・フェルド (Dr.ラーマン)
レオナ・ロバーツ (ゴガーティ夫人)
ジョージ・アーヴィング (ピーボディ)
ヴァージニア・ウォーカー (アリス・スワロー)
ジョン・ケリー (エルマー)
ストーリー
博物館に勤める古生物学者のデヴィッド(ケーリー・グラント)は、4年もかけて復元してきた恐竜(ブロントサウルス)の化石の最後の欠片である「肋骨の骨」が届くのを待ちわびていた。彼は翌日に結婚を控えていたが、博物館への多額の寄付を引き出すため、資産家の代理人とゴルフ場で会うことになる。
そこで彼は、あまりにも自由奔放な令嬢スーザン(キャサリン・ヘプバーン)と出会う。彼女はデヴィッドの車を自分のものだと言い張って走り去ったり、ゴルフボールを奪ったりと、彼の理路整然とした生活を瞬く間に混乱に陥れる。さらに、スーザンのもとにブラジルから「ベビー」という名前の懐っこい豹が届いたことで、デヴィッドはさらに厄介な騒動に巻き込まれていく。
ようやく届いた大切な「恐竜の骨」を、スーザンの飼い犬ジョージが庭に埋めてしまうという最悪の事態が発生。デヴィッドは骨を探してスーザンの屋敷の庭を這いずり回る羽目になる。さらに、ペットの豹「ベビー」と、動物園から脱走した本物の「凶暴な豹」が入れ替わってしまい、町中を巻き込んだ大捕物が幕を開ける。
二人は豹を捕まえようと奮闘するが、不審者として地元の警察に逮捕されてしまう。牢屋の中でもスーザンは支離滅裂な嘘をついて場を混乱させるが、最終的にはスーザンの叔母が寄付金の出資者であることが判明し、誤解は解ける。
後日、恐竜の骨を見つけ出したスーザンが博物館のデヴィッドのもとを訪れる。彼女のあまりのバイタリティに、デヴィッドが必死に組み上げた恐竜の骨格標本は無惨にも崩れ落ちてしまう。しかし、その瓦礫の中でデヴィッドは、彼女なしの人生はあまりにも退屈であることを悟り、ついに彼女への愛を認める。二人は崩れた化石の上で、騒々しくも幸せな結びつきを誓うのだった。
エピソード・背景
- 完璧な掛け合い
ハワード・ホークス監督は、二人の台詞のスピードを極限まで早め、重なり合うような会話劇を演出しました。これが後のコメディ映画のスタンダードとなります。 - 本物の豹との撮影
撮影には「ニッサ」という名の本物の豹が使われました。キャサリン・ヘプバーンは全く動じず、豹を可愛がっていましたが、ケーリー・グラントは恐怖のあまり、豹と一緒のシーンでは代役を立てるよう懇願したといいます。 - 「ゲイ」という言葉の初出
劇中でデヴィッドがフリルの付いた女性用ナイトガウンを着て「突然ゲイ(陽気)な気分になったんだ!」と叫ぶシーンがありますが、これは映画史において「Gay」という単語を現代的な意味合い(性的マイノリティの含み)で使った最初の例の一つと言われています。 - キャサリンのコメディ修行
撮影当初、舞台出身のキャサリンは笑いを取ろうと大げさな演技をしていました。見かねたホークス監督は、ベテランのコメディ俳優をコーチに招き、「笑わせようとするな、真剣に困惑しろ」と彼女を叩き直したことで、あの絶妙なボケ役が完成しました。 - 脚本の妙
脚本家のダドリー・ニコルズらが、知的な語彙とドタバタ劇(スラップスティック)を融合させ、洗練された笑いを作り上げました。 - 興行的な失敗からの逆転
公開当時は赤字となり、キャサリン・ヘプバーンは「興行の毒」という不名誉なレッテルを貼られてしまいます。しかし数十年後、テレビ放送などを通じて爆発的な人気を博し、現在では映画史に残る「完璧な脚本」と讃えられています。 - 恐竜の骨の正体
デヴィッドが一生懸命探していた「肋骨(intercostal clavicle)」という骨の名称は、実は解剖学的には存在しない造語。そんな架空の骨に必死になる学者の姿そのものが、ホークス監督の仕掛けたユーモアでした。
まとめ:作品が描いたもの
本作は、ガチガチの理論で生きる「理性(デヴィッド)」が、圧倒的な「本能と混沌(スーザン)」に屈服し、それを愛として受け入れる過程を鮮やかに描いています。
スーザンというキャラクターは、当時の自立し始めた女性像の極端なパロディでもあり、彼女に振り回されるデヴィッドの姿は、観客に解放感を与えました。論理が通じない世界でこそ、真の自由と愛が見つかるという、喜劇の王道を行く一作です。
〔シネマ・エッセイ〕
「私と一緒にいると、なぜかいつも面倒なことが起きるわね」と笑うスーザンに、デヴィッドが「起きるんじゃない、君が起こしてるんだ!」と絶叫する。このやり取りこそが、この映画の魅力を凝縮しています。
全編にわたって流れる音楽のような台詞の応酬、そして「ベビー」という愛らしい豹がもたらす非日常感。モノクロ映画であることを忘れるほど、画面からは色彩豊かなエネルギーが溢れ出しています。
ラストで恐竜の化石がガラガラと音を立てて崩れるシーンは、デヴィッドが守ってきた古い自分自身の殻が壊れる音でもあります。失ったものは大きいけれど、手に入れたものはそれ以上に素晴らしい。そんな人生の皮肉と喜びを、最高の笑いで包み込んでくれる、まさに宝石のようなコメディです。