赤い靴
The Red Shoes
(イギリス 1948)
[製作] エメリック・プレスバーガー/マイケル・パウエル/ジョージ・R・バスビー
[監督] エメリック・プレスバーガー/マイケル・パウエル
[原作] ハンス・クリスチャン/アンデルセン
[脚本] エメリック・プレスバーガー/マイケル・パウエル/キース・ウィンター/マリウス・ゴーリング
[撮影] ジャック・カーディフ
[音楽] ブライアン・イースデイル/ケニー・ベイカー
[ジャンル] ドラマ/恋愛
[受賞]
アカデミー賞 カラー美術監督・装置賞/劇・喜劇映画音楽賞
ゴールデン・グローブ賞 作曲賞
キャスト

モイラ・シアラー
(ヴィクトリア・ペイジ)
アントン・ウォルブルック (ボリス・レルモントフ)
マリウス・ゴーリング (ジュリアン・クラスター)
ロバート・ヘルプマン (イワン・ボルスラフスキー)
レオニード・マシーネ (グリシャ)
アルバート・バサーマン (ラトフ)
リュドミラ・チェリーナ (イリーナ・ボロンスカーヤ)
エスモンド・ナイト (リヴィンストン)
概要
『赤い靴』(The Red Shoes)は、1948年に公開されたイギリスのバレエ映画で、マイケル・パウエルとエメリック・プレスバーガーが共同で監督・脚本・製作を担当した作品だ。ハンス・クリスチャン・アンデルセンの同名童話を原作としており、バレエと恋愛の間で葛藤する若きバレリーナの悲劇を描いている。
ストーリー
ヴィクトリア(ヴィッキー)・ペイジは、社交界に生きる上流家庭の女性でありながら、バレエへの情熱を抱えていた。偶然のきっかけで、バレエ団の団長ボリス・レルモントフと出会い、彼女の才能に目を留めたレルモントフは、ヴィッキーを自らのバレエ団に招き入れる。同じ頃、若き作曲家ジュリアン・クラスターもまた、レルモントフのもとで働き始める。
バレエ団では、ヴィッキーがレルモントフの目指す「完璧な芸術」を体現する逸材として育成されていく。そして、ジュリアンの作曲による新作バレエ『赤い靴』が制作されることが決まり、ヴィッキーはこのバレエで主役に選ばれる。『赤い靴』は、踊ることを止められなくなった女性がやがて破滅へと向かう物語であり、ヴィッキー自身の人生と奇妙に重なっていく。
レルモントフの指導のもと、ヴィッキーは見事なパフォーマンスを披露し、一躍スターとなる。しかし、バレエ団での成功が続く中で、ジュリアンとの関係が徐々に深まっていく。やがて二人は恋に落ちるが、レルモントフは芸術に全てを捧げるべきだと考え、二人の恋愛を激しく非難する。ヴィッキーは、バレエへの情熱とジュリアンとの愛の間で葛藤するようになる。
やがて、レルモントフとの衝突が激化したヴィッキーは、バレエ団を離れ、ジュリアンとともに新たな生活を始める。しかし、彼女の心にはバレエへの未練が残り続け、芸術への情熱と愛する人との平穏な生活との狭間で揺れ動く。最終的に、ヴィッキーは再び舞台に立つ決断を下すが、彼女の選択は、運命を大きく変えてしまう結果をもたらす。
この物語は、夢と愛の間で揺れる人間の葛藤を描きつつ、芸術に生きることの喜びと苦しみを鮮やかに映し出している。
エピソード
- レルモントフのキャラクターは、実在のバレエ・リュスの創設者であるセルゲイ・ディアギレフをモデルにしていると言われている。
- 主演のモイラ・シアラーは、当時スコットランドのバレエ団で活躍していたプロのバレリーナであり、本作が映画デビュー作となった。
- 映画内のバレエシーンは、実際のバレエ公演のように撮影され、約17分間にわたる長編のダンスシーンが特徴的である。
- 撮影監督のジャック・カーディフは、本作の鮮やかな色彩表現で高い評価を受け、後にアカデミー賞撮影賞を受賞した。
- 映画公開当時、日本では1950年に公開され、有楽座での上映は全席指定という異例の形式で行われた。
- 本作は、マーティン・スコセッシ監督がデジタルリマスター版の制作に関与し、2009年のカンヌ国際映画祭で初公開された。
- 劇中で使用された「赤い靴」は、特注で製作され、現在も映画史上の象徴的なアイテムとして知られている。
- モイラ・シアラーは、本作の成功後もバレエダンサーとしての活動を続け、映画出演は限定的であった。
- 映画の成功により、当時の日本ではバレエブームが起こり、多くのバレエ教室が開設された。
- 劇中のバレエシーンは、特撮技術を駆使して幻想的な演出が施され、観客を魅了した。
感想
『赤い靴』は、静かに心を揺さぶる映画だった。ヴィッキーがバレエへの情熱と愛の間で苦しむ姿はとてもリアルで、彼女の選択に思わず考え込んでしまう。どちらかを選ぶことの重さや、それがもたらす結果に胸が痛む場面も多かった。
映像の美しさやバレエシーンの迫力は言葉にできないほど素晴らしく、夢と現実の狭間を見せつけられるようだった。芸術に生きることの意味を静かに問いかけてくる、心に残る一本だと思う。

















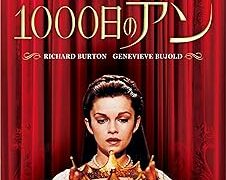









コメント